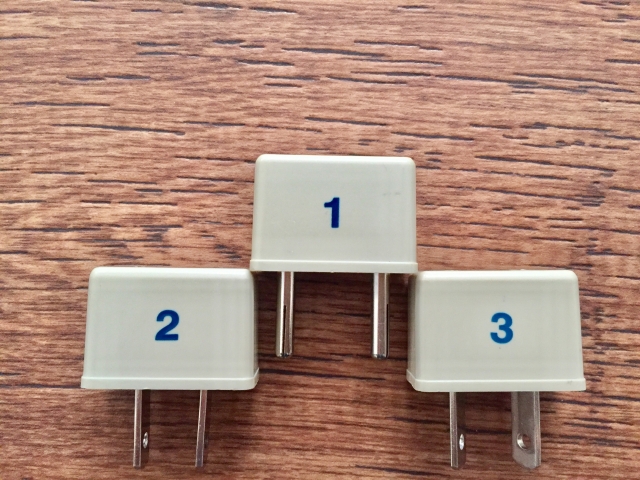ニカド電池とリチウムイオン電池はどちらも二次電池
まず最初に電池には充電できるものと出来ないものがあり、充電出来ない方を一次電池と呼び充電可能なのは二次電池と呼びます。今回取り上げるニカド電池とリチウムイオン電池はどちらも充電が可能なので、同じ二次電池に分類されます。電池はイオン化傾向の異なる2つの物質を電解液に漬けて、この物質が電解液に溶け出していく際に出てくる電子を取り出して電気にしているのです。
この反応は酸化還元反応の一種ですが、電池の構造上電気を加えてやれば逆の反応を起こすことが出来るものが二次電池になります。逆の反応が起こればつまり電気を貯めることが出来るというわけですので、蓄電池と呼ばれることもあります。
二次電池にはこの2つの他にも車のバッテリーに多用されている鉛蓄電池や、太陽光発電などと組み合わせて自然エネルギーの安定供給に一役買うと期待されているNAS電池などがあるのです。その他にも充電できるタイプのものはあるのですが、安全性やコスト面で用途が限られるなど課題もあります。

ニカド電池はリチウムイオン電池とどこがどう違うのか
もともとは蓄電池といえばニカド電池が主流でしたが、最近はリチウムイオン電池の方が主流になりつつあります。実用化されたのはニカド電池の方がはるかに早く、電池の交換が簡単ではない機器の内蔵電池として主に利用されてきました。放電できるぎりぎりまで安定した電圧電流を放電し続けられるのが、ニカド電池の最大のメリットといえます。
しかしながらカドミウムは有害物質である事や、充電の仕方によっては電気を貯めこむ能力が急速に衰えてくることなどが弱点です。また、小型軽量化にもある程度の限界があります。リチウムイオン電池とニカド電池の最大の違いはここで、リチウムイオン電池は小型軽量化をできる点がメリットです。
半面リチウムイオン電池は取り扱いが難しく、製品から発火するといった事故も起こる危険性があります。ニカド電池ではこうした制御や管理の難しさが比較的小さいのも、大きな違いのひとつにあげられるでしょう。

まとめ
以上、ニカド電池とリチウムイオン電池の違いをご説明してきました。開発に貢献した吉野博士がノーベル賞を取るなど、後発のリチウムイオン電池が注目される事も多いですが、コストや安定性などニカド電池はリチウムイオン電池との違いに着目して、電動工具の蓄電池や家庭用小型ソーラー外灯用などの用途で幅広く利用され続けています。
それぞれが特性を活かせる分野で住み分けが行われる状況が今後も当分は続いていくことでしょう。